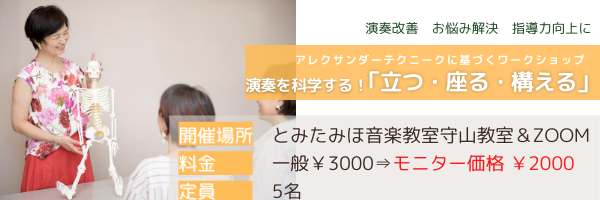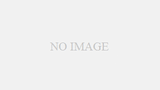ボディシンキング&シンキングボディコーチ
ソプラノ歌うたい冨田美穂です。
週末、アレクサンダーテクニークスクールBODYCHANCEの康裕さんのレッスンに3コマ参加して。
そのあと、康裕さんの個人的なレクチャーにも1コマ出席して、お勉強をしてきました。
(アレクサンダーテクニークって言葉、長いので、以下ATと略します。)
アレクサンダーテクニークの、基本中の基本
アメブロにも書いたのですが、
- アタマが上にいくってどういうこと?
- 身体全体がついてきて…ってどういうこと?
という、アレクサンダーテクニークの基本に関して、また、あたらしい視点を手に入れた、そんなレッスンだったように思います。
この場合の「アタマ」って、どこのことをどういう風にイメージするのか。
身体全体ってどういう風なイメージなのか。
これって、先生方お一人お一人によって、どうも違っているように感じています。
なので、「康裕さんの場合はこう考えてるんだな」と思った、という書き方のほうが、近いかもしれない。
私は、今まで、
・後頭部の筋肉が上へスライドするようなイメージ
・アタマの上の方の空間を高く高くと意識する
っていう印象だったんです。
みたいな言い方をされる部分は、
実際に、脊椎などの骨格をイメージしていました。
でも、どうも、康裕さんの言っていることは違うらしい。
アタマが上に行くってことは、身体全体が一緒に引き上げられるんだよ
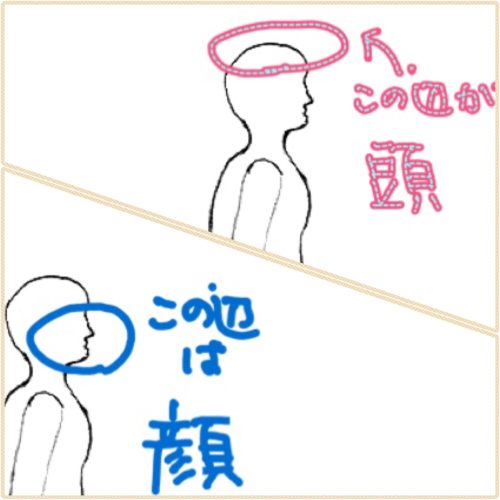
と、 からだ全体は、大きな膜(ファシア Fascia)で覆われているので、全体も一緒に引っ張り上げられるんだよ。
レッスン全体から、そんなメッセージを受け取ったように思います。
ファシアFasciaに関するレクチャーを、ATレッスン3コマの後で受けたので、「ああ、康裕さんあの時の説明はこれが言いたかったのか!」と後から納得した部分がいくつもありまして。
今まで、いろんな先生から同じ指摘受けてきたよなぁ。。。と思う部分の、解決の糸口になったような気が。。。
アタマが上に行っているのに、肋骨や胸郭がついて行ってなかったな。
ファシアのレクチャーを受けて、一晩寝て。
月曜日の仕事の中できがついたのですが、アタマが上に、はいつも思っているのに、胸郭(肋骨エリア)がついて行っていなかったんだな。
つまり、身体全部がついていけていなかったんだな。
どんな先生にも、胸郭をもっと持ち上げるように、というような、提案をされていたんです。ハッキリ口には出されないけれど、手が、そちらに導いてくれる。
お仕事の中で、ピアノを弾いているときに、「あれ?肋骨をさげてるかも??」と気が付いて。
意識的に、アタマは上、身体も上(康裕さんバージョン(笑))、と思ってみたんですね。
そしたら、肩が全然違う位置に移動したんです。
もちろん、上の方にね。
しばらく、目線は変わるわ、視界が変わるわ、重心も変わるわ、で、ぐるんぐるんしたんですが、音楽が全然変わった。
手は動きやすくなったし、
視界が扱いやすくなったし、
いつもだったら慌てるところで、パニックが来なくなった。
「・・・しない」はよろしくない。
ちょっと驚くほどの変化です。
ピアノも、弾くときの姿勢として、「肩はあげない。」ってそういえば言われてたな。
歌う時にも、吹奏楽でも「肩はあげません」って教えられたな。
バレエに至っては、「肩は下げましょう」ですからね。
「肩を下げる」っていうのは、私の中では当たり前以前の習慣だったようです。
「肩を下げる」と、そのすぐ下にある 肋骨エリア 全部が下がりますのでね。。。。
・・・しない、っていう自分への指示はよくないと知ってるけど、根付いて習慣になってるのがこんなにあるんだなぁ。。。